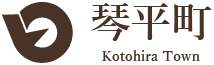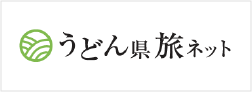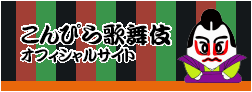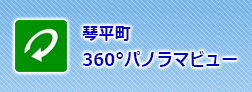こんぴら歌舞伎<外部リンク> こんぴーくん<外部リンク> ふるさと納税 こんぴらにんにく こんぴら石段マラソン 子育て世代包括支援センター 移住・定住補助金一覧リーフレット
本文
令和5年度施政方針
令和5年度施政方針
町政一般報告につきましては、令和4年11月から令和5年1月までの執行状況につきまして、書面にて報告させていただきます。
さて、今定例会におきまして、令和5年度の一般会計予算案をはじめとする各特別会計予算案をはじめ 各議案の提案、ご審議をお願いするに当たり、私の町政運営に向けての施政方針と、主要施策の大要について申し上げ、議員各位並びに、町民の皆様のご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
昨年6月1日より、琴平町長として二期目の就任以来、9か月が経過いたしました。
令和2年から始まりました世界的な災害ともいえる新型コロナウイルス感染症との長い戦いに加え、1年前のロシアのウクライナ侵攻や昨年急速に進んだ円安の影響による物価高騰といった背景 が絡まり、多岐にわたる支援策を行いました。本町においても独自の事業として、小規模事業者応援金、農業者支援応援金、プレミアム付商品券発行、プレミアム旅行券発行、子育て世帯への給付金、小中学校への抗原検査キットの購入、公共施設の感染対策、など一人一人の町民の皆様に寄添いながら、町民の皆様の生活支援、事業者の皆様の事業支援などに取り組みました。
また、5月末には、四国金毘羅ねぷたまつりを開催し、久しぶりに多くの人が集まり、楽しむ人々の姿で賑わいました。夏休みも第7波が7月から9月にかけて感染拡大したものの、夏以降に政府は特に行動制限を取らない感染対策となり、人の交流も徐々に増え、秋には地域のお祭りも縮小した形で開催するところが多くありました。特に県民割が10月から全国旅行支援がスタートし、年末年始を含めて多くの観光客が来町され、また3年ぶりの様々なイベントや会議が開催されております。第8波の感染拡大も10月以降に始まり、現在はピークを過ぎ、落ち着きつつあります。
こうした中、政府は1月末に、5月8日から新型コロナウイルス感染症を感染症法上のこれまでの「2類」から「5類」感染症に位置付けることを決定し、これにより、感染者や濃厚接触者らの待機期間は撤廃され、医療は段階的に通常の体制に移ることになり、コロナ対応は社会経済の正常化に向けて、大きな節目を迎える事となります。また、マスクの着用につきましても3月13日から屋内・屋外を問わず個人の判断に委ねる方針を決定しました。このようなことから、令和5年度においては、これまでの感染対策方針が大きく転換されたことから、本町といたしましても、これまで中止・縮小されていた会議や会合、行事やイベントにつきましては、通常通りに遂行していくこととなります。しかしながらすべてを元通りにするというよりも、改めてその開催目的や内容の確認や見直しをしたうえで取り組むべきと考えております。
二期目にあたり、私が心がけていることは、現場に赴き、そこで見て感じたことを大切にしながら、町政運営を進めていくことであります。
今の時代を生きる私たちが、今後の琴平町のために、今、何をやるべきなのか、それを政策判断の基軸に、次世代への責任ある選択を果たしてまいる覚悟でございます。
今後も、より多くの皆様に、琴平町が進めるまちづくりへの「希望」や「共感」をいただきながら、琴平町への愛着と誇りを持てる、そのような取組を進めてまいりたいと考えております。
日本全体で少子化・高齢化・人口減少化の傾向にありますが、本町ではその傾向を緩やかにしなければならないことは、課題であります。様々なデータをもとに、効果的な施策を短期的中期的に取り組まなければなりません。昨年に町民に付託いただきました重責にお応えするべく、現状において、すべきことを主眼に新年度事業を編成いたしました。
【施策の大要】
令和となり5年目を迎えました。
この間、新型コロナウイルスによるパンデミックと向き合うことで、多くの困難と危機に直面しましたが、同時に本町の持つ底力や多くの価値を再認識させられたことも確かであります。
ワクチン接種を行うにあたり、町民の皆様の協力はもとより、接種を行う医療機関、それぞれが持つ力を大きな目的のために、連携、協働して取り組むことができました。この得難い貴重な経験は、今後も本町の未来に息づいていくはずです。
危機に際して、底力を発揮したのは町職員も同様です。この3年間、国や県から示される数々の施策はいずれも緊急的な対応が求められました。町議会にもご理解をいただき、困難に直面する多くの町民の不安を取り除くために、経験のない事務事業を正確かつ、何よりスピードを重視して、対応することができました。
絆を大切に、心豊かに支え合う町民の存在、いざという時に果敢に立ち向かう職員の力、そして、揺らぐことのない住みやすいまちとしての本町の力、これらは本町が今後も持続的な発展を遂げるために必要な力であり、可能性であります。こうした力や可能性を一つでも多く見出し、社会を前向きに、そして、時代に合わせてより良く変えていくことこそが我々の仕事であり、責任であります。
さて、令和5年度の予算案についてですが、昨年6月に国において示された「経済財政運営と改革の基本方針 2022」では、民間需要に力強さを欠く状況にあって、海外への所得流出を伴う物価高騰や、ロシアによるウクライナ侵略による安全保障環境の変化を踏まえ、景気の下振れリスクにしっかり対応し、民需中心の景気回復を着実に実現することで、成長の分配の好循環に向けた動きを確かなものとしていくとしています。
また、地方財政については、地方公共団体が新型コロナウイルス感染症に対応するとともに、デジタル変革の加速やグリーン化の推進、地方への人の流れの強化等による活力ある地域づくりの推進、防災・減災、国土強靱化を始めとする安全・安心なくらしの実現、人への投資など、持続可能な地域社会の実現等に取り組むことができるよう、安定的な税財政基盤を確保するとして、地方一般財源の総額が令和4年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保することとされました。
一日も早い新型コロナウイルス感染症の克服に取り組むとともに、コロナ後の社会の変化を見据えて、本町が引き続き、持続可能なまちとして、町民の皆様の期待に応えることができるよう編成したところであります。
それでは、これらの考えをもとに、令和5年度に取り組む施策について第5次琴平町総合計画(基本目標)に沿って、ご説明を申し上げます。
1.笑顔で元気なまちづくり(保健・福祉・教育・文化・町政運営)
福祉に関する取組
高齢化率が約40パーセントである本町の現状では、高齢者の生きがいづくりや、健康寿命延伸のための取り組みが重要です。
新年度においては、地域福祉計画や健康増進計画の策定も予定しており、さらなる福祉の推進を図るとともに、住民主体の団体による生活援助として、日常生活に対する簡易な援助を行うサービスも開始する予定としています。今後、認知症高齢者の増加も見込まれることから、早期発見・保護のためのSOSネットワークを構築し見守り強化を行うとともに、認知症施策推進大綱を踏まえ、認知症に対する正しい理解が町全体に広がるよう、普及啓発に努めてまいります。
また、災害発生時における、社会的弱者(要支援者)に対する適切な避難支援に対しても、地域の特性や実情を踏まえつつ、一人でも多くの避難行動要支援者の生命と身体を守るため、取組みを進めてまいります。
子育て支援に対する取組
子育て相談・支援の充実により、子育てしやすいまちを目指すとともに、未来を担う人づくりに向けて取り組んでまいります。令和4年度より「認定こども園」がスタートいたしました。新年度においては、さらなる保育環境の充実や子育て支援の充実のため、空調設備の更新を行うとともに、保護者の負担軽減を目的として、こども園での使用済の紙おむつのご自宅への持ち帰りを廃止し、自園で処理することとします。
保健事業に対する取組
住民の健康づくりに対する意識を深め、まちぐるみで健康づくりに取り組んでいくため、第3次琴平町健康増進計画及び食育推進計画を策定します。また、第2次琴平町自殺対策計画を策定し、コロナ禍により人と接する機会が急激に減ったことによる孤独や経済的不安により自殺に追い込まれることのないまちを目指して自殺対策にも取り組んでまいります。
母子保健においては、新年度より「出産・子育て応援交付金」の支給のほか、「コウノトリ応援事業」の補助を開始するとともに、産前産後のサポートなど、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援に引き続き取り組んでまいります。
教育に対する取組
教育は、人格の完成を目指し、心身ともに健康な国民の育成を期して行うことを目的に、学校教育や社会教育などにおいて行うことになっています。学校教育においては、次年度も教育委員会が進めている「自立に向かう教育の推進と行きたくなる学校・学級づくり」を一層推進し、次代を担う子どもたちの自主性と創造性を培うとともに確かな学力を身に付け、豊かでたくましい心と体を育てる教育の充実に努めてまいります。
そのため、これまで整備してまいりました児童生徒一人一台の夕ブレット端末や大型電子黒板等を十分に活用することによって、すべての児童生徒がより質の高い教育を受け、必要なスキルの習得を実現することに努めているところであり、新年度においても次世代を担う子どもたちにICTを活用して新しい時代に必要な資質・能力を育んでまいります。
また、これまでに引き続き、小中連携による英語学習の推進を図るとともに、英語力向上のために英語検定の受験料の補助も進めてまいります。
そのほか、自己肯定感や自己有用感の醸成をあらゆる場面を通じて行うとともに、不登校などの悩みを持っている子供たちへの支援を積極的に進めてまいります。
なお、ふるさとことひらを愛する教育や様々な人権問題について主体的に解決する児童生徒の育成については、これまでの成果をさらに積み上げられるように取り組んでまいります。
さらに、町としての一貫した教育理念のもと、共通認識をもって教職員が指導に当たり、子どもたちが互いに学び合い、切礎琢磨できる充実した教育環境を提供できるよう、子どもたちが日常の学校生活を送る場となるこども園、小学校の整備・統合についても進めてまいります。
一方、社会教育においては、生涯教育や家庭教育の大切さを共有するための取組や支援について、検討し、小さな子供からご高齢の方に至るすべての方が生涯にわたって学び続けることができる環境の整備に努めてまいります。
新年度においては、琴平町公園長寿命化計画の策定や、ヴィスポ琴平の整備を進めてまいります。
ところで、令和の耐震対策工事後、旧金毘羅大芝居金丸座の縦覧が再びスタートし、魅力ある重要文化財として、多くの方々にご覧いただいております。旧金毘羅大芝居を含め、文化財の保護・活用に関する取り組みについて、町文化財保護協会とともに、徐々にではありますが進めております。新年度では、より具体的な取り組みを整理しながら、歴史と伝統、文化のかおる町づくりを推進してまいります。
いこいの郷公園に対する取組
平成16年にオープンいたしました、いこいの郷公園 ヴィスポ琴平ですが、現在ことひらいこいの郷パートナーズを指定管理者として、運営をいたしております。その期間が令和6年3月末で終了することから、令和6年4月以降の運営について、新年度において指定管理者の公募等を進めてまいります。また、施設については経年劣化等による不具合等を防ぐため、必要な改修や修繕を順次進めて参ります。
町政運営に対する取組
人口減少がさらに進行すると見込まれる中、持続可能な行財政運営と質の高い行政サービスを次世代に引き継ぐためには、本町の公共施設等の見直しを早期に図り、効率的かつ効果的な維持管理や最適な配置を実現しなければなりません。公共施設の整備方針を早期に確定する声は、議会だけでなく保護者や町民の多くから寄せられており、その期待に応えられていないことは申し訳なく存じております。
新年度においては、特に小学校の統合については町長部局と教育委員会が連携して進めてまいります。小学校とこども園の位置や建設について保護者の声をききながら、半年後を目途に、確定させたいと考えております。そのため町長部局が主導いたしますが、保護者や教員などの関わりなどから教育委員会も関係することなので、教育委員会に、小学校の再編に関する室を併設し、町長部局とも連携して進めていきたいと考えております。
また、未耐震である町庁舎の在り方を含め、その他の公共施設についても、検討を進めてまいります。
若者の未婚化、晩婚化及び少子化傾向への対応につきましては、県が進める出会いサポート事業である縁結びマッチングシステムへの登録促進など、広域による結婚支援を推進してまいります。また、老朽化した公民館施設への対応として、新年度に中央公民館のエレベータの更新や琴平公民館のエアコン更新を行うこととしています。
国では、「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」を目指す「デジタル田園都市国家構想」の実現に向け、デジタル技術の活用によって、地域の個性を生かしながら地方の社会課題解決や魅力向上の取組を加速化・深化することとしています。 本構想の実現を図るため、国においては、今般、第2期「まち・ひと・しご と創生総合戦略」を抜本的に改訂し、2023 年度を初年度とする5か年の「デジタル田園都市国家構想総合戦略」を新たに策定し、閣議決定されました。地方においては、まち・ひと・しごと創生法第9条及び第10条に基づき、国の総合戦略を勘案し、都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び市町村まち・ひと・しごと創生総合 戦略を策定するよう努めることとされています。本構想の実現に当たっては、国と地方が連携・協力しながら推進することが必要であり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大やデジタル技術の浸透・進展など時宜を踏まえ、地域の個性や魅力を生かした地域 ビジョン、地域が目指すべき理想像を再構築した上で、地方版総合戦略の策定、改訂に努めなければなりません。そこで、私はこの琴平町は行政の立場として地域経営する視点が肝要であると考えており、町には、第5次琴平町総合計画を指針にまちづくりを進めておりますが、より具体的で明確な目標を決めることにより、職員も町民も同じ方向に向かって、一丸となって人口減少やコロナ禍からの回復など、この危機的状況を脱する良い機会であると考えております。国・香川県の総合戦略を勘案しながら、デジタルだけではなく、地域課題の解決を目指したわかりやすい琴平町の総合戦略を新年度の中には着手していきたい所存です。
また、行政のデジタル化についても、早急な取組みが求められています。昨年度においては、庁内の「文書管理・電子決裁システム」を導入し運用を開始しました。さらに、テレワーク環境の整備や庁内のネットワークアクセス環境の向上を図ること等により、職員の働きやすさと働きがいの向上を図ったところです。新年度においても、国の「自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画」の方針を踏まえながら、自治体における情報システム等の共同利用や手続きの簡素化、迅速化、効率化を進めるため標準仕様との比較分析を行い、国が策定する標準仕様に準拠したシステムへの移行に向け準備します。加えて、多様化・複雑化する行政課題に柔軟に対応するため、「公」と「民」との連携を推進し、行政コストの削減を図りながら、質の高い公共サービスの提供を目指します。
また、「おつりのいらない町 琴平町」をスローガンのもと、令和3年12月に県内初となる電子地域通貨「KOTOCA」事業がスタートしました。新年度には、国のデジタル田園都市国家構想交付金を活用し、電子地域通貨「KOTOCA」事業を推進するとともに、高齢者に対するがスマートフォンを新規に購入した際の補助事業をはじめ、スマホ教室の開催など、高齢者のデジタルデバイド(インターネットやPCなどを活用できる人とできない人の間に生まれる格差)の解消に取組んでまいります。
ふるさと納税に対する取組
ふるさと納税は、個人が居住している地域「以外」の特定の自治体に寄附をし、住民税等の控除や、その地域の名産品などの返礼品を受け取ることができる制度です。自治体にとっては、地域の税収増となり得る取り組みです。また、地元事業者の売上の増加支援、琴平町と関わり、地域を応援するリピーター、ファンが増える。周辺自治体と連携協力することにより課題解決を広域的に取り組めるなどが見込まれます。
本町ではここ数年は、およそ寄附額が五千万円であります。先進地の自治体では、数億円から数十億円もの寄附が毎年あり、それを財源に地域課題の解決の事業に新たに取り組んでいます。
本町といたしましても、商品返礼品の開発、PRの仕方の工夫、情報の発信など、改良することによりまだまだ寄附額の増加の可能性があることから、積極的に取り組む所存です。
2.にぎわいのあるまちづくり(観光・経済)
観光・経済に対する取組
度重なるコロナ禍の長期化により、町内にある事業所においては、今もなお、逼迫が強いられている状況にあります。そうした緩和施策として新年度においては、従来の町活性化事業(プレミアム商品券など)を、より利用しやすいよう取組むとともに、国による物価高騰対策を注視しつつ、本町への影響を適切に把握し、必要な場合には町民などに対し、必要かつ効果的な対策を検討してまいります。
また、地域おこし協力隊員を増員し、本町の情報発信や地域ブランドや地場産品の開発・PR等を行っていきます。
農業に対する取組
我が国の農業は、農業従事者の著しい高齢化、後継者や担い手の不足に加えて、コロナ禍による需要の低迷や価格の下落、ウクライナ情勢による資材費の高騰など以前にも増して厳しい状況となっています。町内にある農地の保全を目的に農地維持管理費補助金を継続して実施するとともに、農産物の品質向上、地産地消、販路拡大等、地域農業の振興、発展を進めてまいります。
観光に対する取組
観光事業につきましては、コロナ禍の収束を見据えて、従来のイベント事業や催物を再開すると共に、コロナ禍時に協議していた観光事業計画案を実施していきたいと思います。
また、令和5年1月より、台湾、香港などの高松空港の就航が再開されました。これにより、インバウンド外国人観光客においても、本町への来町者数も増加が見込まれることから、ポストコロナに向けた対策が必要となってまいります。そして、2025大阪・関西万博や瀬戸内国際芸術祭を見据えたうえで、受入れ態勢を整えて、諸外国から来町された方々には、ISO規格を基準とした分かりやすい案内表記などインフラ整備を実施していきたいと考えています。
また、四国こんぴら歌舞伎大芝居については、全国にある芝居小屋では、コロナ禍により、現在、慣例となっています、それぞれの歌舞伎公演を余儀なく中止や見送りになっているところが大半を占めています。そうした状況の中、コロナが収束傾向にあり、規制や行動制限が緩和されるなど、徐々にではありますが、事業再開に向けての取組みをしている団体もございます。本町においても、四国こんぴら歌舞伎大芝居の再開に向けて、来春には第37回公演の実施に向け協議・準備を進めてまいります。
今後においても、費用対効果を考慮しながら各事業を分析・精査した上で、最善の観光・経済対策をとってまいります。
3.安全・安心なまちづくり(防災・環境・住民生活・インフラ整備)
環境に対する取組
「脱炭素社会」への機運醸成に向けた取組として「COOLCHOICE(クールチョイス)」宣言に基づく各種啓発事業について令和4年度より取組みを開始いたしました。また、環境対策に優れた「電気自動車」の普及に向けて、庁舎公用車としては初めての「電気自動車」の導入や、災害時にも活躍できる外部給電設備の中央公民館への導入を行うなどPRに努めたところです。
今後においても、ゼロカーボンシティの実現に向けて、エネルギーの地産地消の推進体制の構築や、再生可能エネルギーの導入拡大など、町民・事業者・行政の連携・協力により、温室効果ガス排出量の削減に向けた取組みを推進します。さらに、これまで続けてきた「家庭用太陽光発電」「蓄電池」「住宅断熱材」などにかかる助成金に加え、新年度には、県内他市町に先駆けまして、軽EV(軽自動車の電気自動車)購入者へも対象を広げたいと考えています。現在、国が実施している補助金に上乗せして交付し、脱炭素社会に向けての機運醸成をさらに加速させます。
また、老朽化が進む塵芥処理施設への対応として、中讃広域行政事務組合や近隣市町と協力しコストの増加を抑える一方で、住民サービスの低下を招くことのないよう取り組んでまいります。新年度においては、塵芥収集車の更新を予定しており、ゴミ収集作業がより円滑に進むよう努めてまいります。
住民生活に対する取組
渇水への対応も必要です、令和4年度は少雨のため早明浦ダムの貯水率が低下し、吉野川水系水利用連絡協議会は香川用水への供給量を50%カットする第三次取水制限を行いました。本町においても渇水対策本部を設置し町民などに対し節水の呼び掛けを行いました。今後においても、水道水の安定供給に向け香川県広域水道企業団と協力するとともに、様々な支援にも取り組んでまいります。
防災・防犯対策については、南海トラフ大地震の可能性がある中、住民の皆様が安心安全に日常生活を送ることができるように防災のまちづくりを推進していくことが重要と考えています。新年度には、防災行政無線の基盤整備を更新するとともに、町消防団においては、香川県消防操法大会へ出場し、地域防災力の要である消防団の訓練等を行います。また、災害発生時に対応するためにも、役場内での災害対策本部の設置訓練、秋には町民や各団体との総合訓練を実施し、いざという時のための意識と行動の向上を図ります。
また、地域や県警とも連携しながら、地域の状況を踏まえた取組みや防犯カメラ設置に対する補助を行うなど街頭犯罪等の発生抑止を目指す取組みを引き続き推進します。
空き家に対しては、新年度において、二度目の空き家実態調査を行います。地域に影響を及ぼす空き家に対しては、「琴平町空家等対策計画」に基づき対処するとともに、効果的な対策について検討を進めてまいります。
また、令和4年度より「町長への手紙」制度を開始いたしました。地域や自治会内においては、少人数世帯・高齢単身世帯の増加が増え、地域コミュニティを取り巻く社会環境の変化、個人の生活様式や価値観も多様化するなど人と人とのつながりの希薄化がみられます。これまで地域で担ってきた自助・共助の機能が低下する一方で、地域課題はより一層複雑・多様化しています。これら問題を少しでも緩和し、住みやすい琴平町となるようこれまで多くのご意見を町民の皆様から頂いております「町長への手紙」により、また、「町民会議」を開催しさらに多くの町課題について語り合い、ともにまちづくりを進める「身近な行政」へと引き続き取組む所存であります。
【最後に】
WHOによるパンデミックの宣言から約3年、新型コロナウイルス感染症は、いまだ予断を許さない状況でありますが、 少しずつ、ポストコロナの兆しも見えてまいりました。翻ってわが国に おいては、激甚化し頻発する自然災害への対策、さらには人口減少、超高齢社会の到来による社会構造の変化への対応など、本町も同様に、様々な課題に立ち向かっていかなければなりません。
これまで多くの先人たちの努力により、築かれた街並みや歴史、伝統や文化、そして緑豊かな自然環境など、いままさに、本町が有するこれらの貴重な財産を次の時代に伝えるとともに、「小さくても、みんなが笑顔で、幸せを感じるまち」実現のため一歩ずつ着実に歩みを進め本町の未来を全力で拓いてまいりたいと思っています。
以上、令和5年度における施政方針といたします。
町民の皆様には、町政に対する一層のご理解をいただくとともに、議員各位には今後ともご指導・ご支援を賜りますようお願い申し上げます。