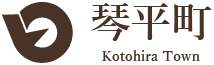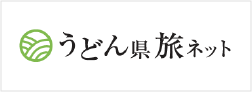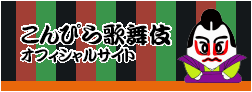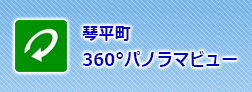詳細検索
注目ワード
こんぴら歌舞伎<外部リンク> こんぴーくん<外部リンク> ふるさと納税 こんぴらにんにく こんぴら石段マラソン 子育て世代包括支援センター 移住・定住補助金一覧リーフレット
本文
令和6年度施政方針
記事ID:0010408
更新日:2025年2月28日更新
令和6年度施政方針
令和6年度当初予算案をはじめ、諸議案のご審議をお願いするにあたり、私の 町政運営に対する基本的な考え方と主要な施策の概要につきまして、説明申し上げ、議員各位及び町民の皆さまのご理解とご協力を賜りたいと存じます。
昨年は、世界中で猛威を振るいました新型コロナウイルス感染症の対策が緩和されて以降、感染防止と社会経済活動との両立、社会経済活動の正常化が求められることとなり、旅行やイベント等人流が活発に動き始め、3年以上にわたるコロナ対策は有事から日常へと、次なる段階を迎えました。 このような中、世界的にも経済活動の正常化が進み、インバウンドに関していえば、琴平の観光は長く厳しい状況からようやく抜け出し、高松空港の台北やソウルなどの国際便の就航再開により、参道に外国人観光客が多くみられるようになりました。秋には、石段マラソンをはじめとする、金刀比羅宮 奉祝奉賛行事を通常どおりに開催し、平日にも関わらず、町内外から多くの参拝者が沿道に来られるなど、賑わいを取り戻しつつあると言えます。
しかしながら、少子高齢化に伴う人口の自然減にも直面しており、想定を超えるスピードで人口減少が進んでおります。町民に多大な影響を及ぼしている物価高騰については、世界的なインフレ等により先行きを見通すことは困難な状況です。このほか、人材・人手不足は深刻さを増しており、地域経済の改善回復の悩みとなっております。あわせて、国が推進しております脱炭素化やデジタル化への急速な進展への対応が求められるなど、本町を取り巻く環境は、コロナ禍前とは大きく変化しています。今後の自治体運営にあたっては引き続き、危機感を持って臨む必要があります。
令和5年度において行った事業を振り返ってみますと、先ずは永年の懸案でもあった、統合小学校、統合認定こども園に対する取組を進めました。「琴平町学校等再編整備検討協議会」に町長、教育長より諮問し、計9回におよぶ協議を経て、小学校及び認定こども園の再編整備に対する答申が出されました。その答申内容を尊重し、町及び教育委員会は、「町総合教育会議」にて「琴平町立小学校・認定こども園再編整備基本方針」を策定し、1月から2月にかけまして、保護者や住民に対する説明会を合わせて6回開催いたしました。今後、保護者や町民の期待に応えるべく整備を進め、子育てしやすい環境づくりや教育環境の充実に努める所存です。
また、国が行う物価高に対する経済対策の給付金の補助対象外となった世帯、いわゆる課税世帯に対しましては、1世帯当たり2万円に相当する2万KOTOCAを、琴平町電子地域通貨であるKOTOCAにて支給するなど、町独自の支援策を行いました。また、高齢者の方には、スマートフォンの購入補助やスマホ教室を開催するなど高齢者の方がスマホへ移行しやすい環境づくりにも取組みました。
子育て支援として、インフルエンザ予防接種費用についても、18歳まで町内医療機関では無料とするなど助成の拡大を行ったほか、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による食料品及び燃料の価格高騰に伴う給食費の単価上昇分につきまして新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当し、子育て世帯の負担を増加させることなく、栄養バランスの取れた安心安全な学校給食の安定的な供給に努めました。
令和6年度の予算案についてですが、昨年6月に国において示された「経済財政運営と改革の基本方針2023」では、「時代の転換点」とも言える構造的な変化と課題に直面する中、30年ぶりとなる高い水準の賃上げや企業部門における高い投資意欲など、足下での前向きな動きを更に力強く拡大すべく、新しい資本主義の実現に向けた取組を加速させ、新時代にふさわしい経済社会の創造を目指していくとされています。
本町においても、この時代の変化に乗り遅れることなく持続可能なまちづくりを念頭に、町民の皆様の期待に応えることができるよう予算編成をおこなったところです。
それでは、令和6年度の施策につきまして第5次琴平町総合計画(基本目標)に沿って、ご説明を申し上げます。
1. 笑顔で元気なまちづくり(保健・福祉・教育・文化・町政運営)
福祉に関する取組
近年、少子高齢化の進行とともに、生活環境や家族形態も変化し、核家族化や単身世帯が増加している中、個人の価値観やライフスタイルも多様化することにより、地域のつながりの希薄化など、地域社会を取り巻く環境が大きく変化し、従来からの子ども、障がい者や高齢者など、それぞれの分野別支援では対応が困難な複合化・複雑化した福祉課題が生じています。
令和6年度においては、それらの複合化・複雑化した支援ニーズに対応する包括的支援体制を構築するための「重層的支援体制整備事業」を創設し、属性を問わない相談支援、参加支援及び地域づくりに向けた支援の3つの支援を一体的に実施してまいります。
また、令和6年1月1日に施行された認知症基本法に基づき、施策の推進・検討を視野に入れた認知症施策の展開を行ってまいります。
子育て支援に対する取組
令和5年12月に、「こども基本法」に基づき、こども政策を総合的に推進するため、政府全体のこども施策の基本的な方針等を定める「こども大綱」が閣議決定されました。
「こども基本法」は、全ての子どもや若者が、健やかに成長でき、将来にわたって幸せに生活できる「こどもまんなか社会」を作っていくための法律です。「こどもまんなか社会」を作っていくために大事にすること。それは、「こどもや若者のみなさんが生まれながらに持っている権利を大切にしながら、皆さんの今とこれからにとって最も良いことを行なって行くこと」や「こどもや若者の皆さんの意見を聞きながら、一緒に進めていくこと」、また、「おとなとして自分らしく生活を送ることができるようになるまで、ずっと、しっかり支えていくこと」などです。
本町においても、「琴平町子ども・子育て支援事業計画」の第2期計画が令和6年度までとなっていることから、第3期計画にむけた見直しを行います。この見直しに際し、「こどもまんなか社会」の実現に向けた取り組みの一端を担えるような事業計画の策定やその実現に向けた取組を行ってまいります。
保健事業に対する取組
健康づくりは、個人個人の「自助努力」が大前提にありますが、豊かで便利な生活の代償として「生活習慣病」が蔓延している今、個人の意識に頼るだけでは限界があり、町民・地域、行政や専門機関が役割分担しながら、町ぐるみで健康を底上げする必要があります。
町民の健康と食育をさらに推進していくために、本年3月に策定いたします「第3次琴平町健康増進計画及び食育推進計画」を踏まえ、町民の健康づくりに対する意識を高め、具体的な行動を実践し、まちぐるみで健康づくりに取り組んでいくこととします。
教育に対する取組
教育は、人格の完成を目指し、心身ともに健康な国民の育成を期して行うことを目的に、学校教育や社会教育などにおいて行うことになっています。
学校教育においては、次年度も教育委員会が進めている「自立に向かう教育の推進と行きたくなる学校・学級づくり」を一層推進し、次代を担う子どもたちの自主性と創造性を培うとともに確かな学力を身に付け、豊かでたくましい心と体を育てる教育の充実に努めてまいります。そのため、これまで整備してまいりましたGIGAスクール構想により、児童生徒一人一台の夕ブレット端末や大型電子黒板等を有効に活用することによって、すべての児童生徒がより質の高い教育を受け、必要なスキルの習得を実現することに努めているところであり、新年度においても次世代を担う子どもたちがICTを活用して新しい時代に必要な資質・能力が身につくように育んでまいります。
また、これまでに引き続き、小中連携による英語学習の推進を図ります。英語に関する「英語指導助手」を現状では小・中学校で1名の配置をしておりますが、英語教育の充実及び国際理解教育の推進を図るとともに、児童・生徒の国際感覚及びコミュニケーション能力を高めるため、1名増員します。なお英語力向上のために「英語検定の受験料の補助」も進めてまいります。
また、令和5年度に再開いたしました台湾新北市瑞芳区ならびに瑞芳中学校との国際交流につきましては、令和6年度には琴平中学校の生徒を台湾に派遣し、姉妹校交流を行います。
そのほか、自己肯定感や自己有用感の醸成をあらゆる場面を通じて行うとともに、不登校などの悩みを持っている子どもたちへの支援を町全体として積極的に進めてまいります。
なお、ふるさとことひらを愛する教育や様々な人権問題について主体的に解決する児童生徒の育成については、これまでの成果をさらに積み上げ、より充実したものになるように取り組んでまいります。
さらに、町としての一貫した教育理念のもと、共通認識をもって教職員が指導に当たり、子どもたちが新しい時代にあった、お互いの学び合いや、切磋琢磨していくことができる充実した教育環境を提供できるよう、進めてまいります。
さて、本年1月9日に、町長と町教育委員会の教育委員により構成しております「琴平町総合教育会議」において、琴平町立の小学校と認定こども園についての「再編整備基本方針」を策定いたしました。
基本方針では、「町立認定こども園と小学校は、それぞれ1つに統合し、琴平町の地理的に真ん中あたりに、施設を併設して、新築する。」といたしました。
私といたしましては、琴平町の子どもたちの未来、また琴平町の教育・保育をはじめ、将来のまちづくりのことを考えると、この問題を、もうこれ以上先送りすることなく、皆様のご理解もいただきながら、子どもたちの教育環境を最優先に考えながら推進していかなければならないと、私の政治生命をかけての強い決意と覚悟を持って、統合認定こども園整備事業ならびに統合小学校整備事業に取り組んでまいる所存であります。
一方、社会教育においては、生涯教育や家庭教育の大切さを共有するための取組や支援について、検討し、小さな子どもからご高齢の方に至るすべての方が生涯にわたって学び続けることができる環境の整備に努めてまいります。
令和の耐震対策工事後、旧金毘羅大芝居金丸座の縦覧が再びスタートし、魅力ある重要文化財として、多くの方々にご覧いただいております。旧金毘羅大芝居を含め、町内に有する文化財の保護、保存・活用に関する取組について、町文化財保護協会とともに、徐々にではありますが進めているところです。天然記念物、大センダンにつきましても、令和5年度末には「大センダン保存活用計画」が策定されることから、令和6年度からはこの活用計画を基に、緑地化等の基本実施計画の策定に取り組みます。今後とも、歴史と伝統、文化のかおる町づくりを推進してまいります。
いこいの郷公園につきましては、平成16年にオープンし、いこいの郷公園及びヴィスポことひらはすでに20年が経とうとしています。指定管理者の公募を行い、令和6年4月以降も引き続き「いこいの郷パートナーズ」を指定管理者として運営を進めてまいります。また、施設の経年劣化等による不具合等を防ぐため、琴平町公園長寿命化計画を策定し、それを基にLED化や遊具の更新などの改修・修繕を順次進めてまいります。
町政運営に対する取組
人口減少がさらに進行すると見込まれる中、持続可能な行財政運営と質の高い行政サービスを次世代に引き継ぐためには、本町の公共施設等の見直しを早期に図り、効率的かつ効果的な維持管理や最適な配置を実現しなければなりません。公共施設の整備については、町民をはじめ多くの方々から声が寄せられており、その期待に応えられていないことは申し訳なく感じています。
令和6年度においては、まず、先に申しましたように町立小学校及び認定こども園の再編整備を進めてまいります。
また、本役場庁舎につきましては現庁舎を耐震化しての活用ができないか調査を行い、その他の公共施設については、小学校及び認定こども園の再編整備に目途がついた段階で、整備方針や方法などの検討を進めたいと考えています。
行政のデジタル化についても、早急な取組が求められています。国は、2023年度を初年度とする5か年の新たな「デジタル田園都市国家構想総合戦略」を閣議決定し、「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」の実現に向け、デジタルの力を活用しつつ、地域の特性を活かしながら地方の社会課題の解決や魅力向上の取組みを加速化・深化することとしています。
本町においても、中讃広域行政事務組合の自治体DX推進事業などを活用しながら、職員の意識向上や業務の洗い出しなどに取り組みます。
また、令和2年度から令和6年度が計画期間となっている「第2期琴平町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を見直し、国の「デジタル田園都市国家構想総合戦略」を勘案し、今年度「(仮称)琴平町デジタル田園都市国家構想総合戦略(令和7年度~令和12年度)」を策定することとしています。デジタルを活用しながら、人口減少対策、地域活性化に引き続き取り組んでまいります。
また、国は自治体における「情報システムを標準化・共通化」し、デジタルを前提とした手続きの簡素化、迅速化、効率化を進めております。本町におきましても、令和7年度末までに、国が策定する標準仕様に準拠したシステムへ、スムーズに移行できるよう中讃広域2市3町で協力し進めてまいります。この自治体情報システムの標準化・共通化により、制度改正のたびに独自でシステム改修を行う必要性や、今後懸念される職員の人材不足などの課題の解消が図られると考えます。
「おつりのいらない町 琴平町」をスローガンのもと、令和3年12月に県内初となる電子地域通貨「KOTOCA」事業がスタートしました。新年度には、引き続き国のデジタル田園都市国家構想交付金を活用し、電子地域通貨「KOTOCA」事業を推進するとともに、高齢者に対するスマートフォンを新規に購入した際の助成事業をはじめ、スマホ教室の開催など、高齢者のデジタルデバイド、つまり、インターネットやPCなどを活用できる人とできない人の間に生まれる格差の解消に取り組んでまいります。
ふるさと納税に対する取組
ふるさと納税につきましては、本町にとって、寄附金は貴重な財源であるものの、ここ数年の本町の寄附額は、年間約5,000万円から6,000万円となっております。そこで、令和5年度に「ふるさと納税支援業務の委託事業者」の変更を行い、ふるさと納税サイトの商品掲載ページの充実化や新規返礼品の掘り起こしなどに取り組んでおります。そして新たにホテルでの「現地決済型」のふるさと納税サイトの導入や新しい返礼品の開拓等を行ってまいりましたが、令和6年度以降においてはこれらに加え、新たなポータルサイトの追加登録、体験型の返礼品開拓などを行い、一層のふるさと寄附金の増額に向け積極的に取り組む所存です。さらに「企業版ふるさと納税」制度を活用し、企業からの寄附金を募ります。企業版ふるさと納税は、企業が地方公共団体の地方創生の取組に対して寄附を行った場合に法人関係税が税額控除される制度であり、企業として地域振興やSDGsの達成などの社会貢献ができるほか、法人関係税の高い軽減効果を受けられるメリットがあることから、このメリットを企業に対しPRすることで、新たな財源の創出に努めます。
近年、地域コミュニティの中心である自治会への加入率が、本町では5割を切る状況にあります。このことは、福祉、防災、防犯など、地域力の低下による不安要素となっております。そこで、地域共生社会を確立する観点からも、行政だけでなく関係団体とともに「地域づくりの懇談会(仮称)」を地域ごとに開催し、住民と連携しながら、話し合い、課題を見出し、それをだれが役割を担うのかなどを共有化することにより、住民にとって安心安全なまちづくりになると考え、推進していく考えであります。
2.にぎわいのあるまちづくり(観光・経済)
観光・経済に対する取組
昨年5月の新型コロナウイルス感染症の5類移行により、感染対策の緩和や国際路線の再開や増便などにより、国内外からの観光客が徐々に増えてまいりましたが、全国的にもコロナ禍前の7~8割程度にとどまっている状況です。コロナ禍の長期化や燃料費や物価の高騰などにより、町内事業者を取り巻く現状は大変厳しいことから、引き続き、プレミアム商品券発行事業やKOTOCAプレミアムチャージポイント付与事業など、個人消費の回復や地域経済の活性化を図ってまいります。
4月には、5年ぶりとなる第37回「四国こんぴら歌舞伎大芝居」を開催し、琴平に春を告げる風物詩の復活・成功、さらには以前のように町内が活気づくことに期待し、その成功に向け、地域や関係者の方々とともに、町全体で取り組んでまいります。
また、2025大阪・関西万博や瀬戸内国際芸術祭を翌年に控え、インバウンドを見据えた受け入れ態勢のさらなる充実や他の自治体との横連携、広域観光の推進など、金刀比羅宮や観光関連団体等と協議を重ねながら、情報の共有化を図り、連携強化により観光地の魅力発信や観光客の誘客事業に取り組んでまいります。
また、地域おこし協力隊員を増員し、令和6年度は従来の会計年度任用職員だけでなく、スピード感を持った積極的な活動を行えるように委託型の地域おこし協力隊制度を導入し、地域活性化を目指すとともに、卒業後の隊員の定住を促進するため、まちづくり団体の設立に向けて取り組むこととしております。また、昨年度より、地域おこし協力隊のX(旧ツイッター)を立ち上げ、本町の情報発信や地域ブランドや地場産品の開発・PR等を行っていきます。
農業に対する取組
我が国の農業は、農業従事者の著しい高齢化、後継者や担い手の不足に加えて、コロナ禍による需要の低迷や価格の下落、ウクライナ情勢による資材費の高騰などの影響が残り、厳しい状況が続いています。町内にある農地の保全を目的に農地維持管理費補助金を継続して実施し、農産物の品質向上、地産地消、販路拡大等、地域農業の振興、発展を進めていくとともに、新年度より収入保険に新規で加入される農家に対し補助することで、持続可能な農業経営の安定を応援してまいります。また、土地改良事業、多面的機能発揮促進事業の予算を拡充する事により、農業施設及び地域環境の保全を行ってまいります。
3.安全・安心なまちづくり(防災・環境・住民生活・インフラ整備)
住民生活・環境に対する取組
「脱炭素社会」への機運醸成に向けた取組として令和4年度以降、「COOLCHOICE(クールチョイス)」宣言や、琴平町地球温暖化対策実行計画に基づく各種啓発事業や補助制度等を続けてきたところでございますが、令和6年度においても、事業者・住民等の取組も含めた区域全体での削減を加速させます。ゼロカーボンシティの実現に向けて、エネルギーの地産地消の推進体制の構築や、再生可能エネルギーの導入拡大など、町民・事業者・行政の連携・協力により、温室効果ガス排出量の削減に向けた取組を推進します。県内他市町に先駆けて昨年度からスタートした「電気自動車購入に対する補助制度(国補助金への上積み)」は、町民はもとより県内他市町からも実施内容の問い合わせが多数あり、本町に追随する動きを見せていることから今年度も継続して実施いたします。
町の家庭ごみ収集(塵芥収集)においては昨年度、町指定ごみ袋の可燃ごみ袋に破れにくい素材のものを導入しました。町民の皆様からご好評をいただいており、令和6年度も小売価格を据え置きのうえ継続する予定です。また、新たに「ハッピーマンデー可燃ごみ収集」を4月からスタートさせます。この「ハッピーマンデー可燃ごみ収集」は、平日が祝日や振替休日に相当する日においても、処理施設の開場日は常に、町職員が収集用務にあたるというものです。これまで、可燃ごみ月・木収集地区の皆様から頂いた要望に応え、新たな処理施設への搬入に向けてのコスト平滑化や、何よりも住民の皆様の利便性を鑑み実施するもので、3月末に配られる「ことひら地区別ごみ収集カレンダー」や「広報ことひら」においても案内予定です。
なお、令和10年度より、ごみ焼却処理施設をクリントピア丸亀に移行の対応といたしましては、引きつづき中讃広域行政事務組合や近隣市町と協力し、コストの増加を抑える一方で、住民サービスの低下を招くことのないよう取り組んでまいります。同時に、資源収集用トラックが老朽化していることから、新たな車両への刷新を予定しており、収集作業がより円滑に進むよう努めてまいります。
さらには4月の「四国こんぴら歌舞伎大芝居」に合わせて、町の塵芥収集員が金丸座周辺や参道筋のゴミ拾い活動を実施します。「KOTOHIRA CLEAN KEEPER」の上着を着用して巡回する収集員は、ポイ捨てごみや食べ歩きごみなどを分け隔てなく収集して「“ごみの無いまち“ことひら」を町内外にPRします。
公共交通機関に対する支援も行う予定としています。安全・安定した運行の維持と利便性・快適性の向上による利用者の増加を図るため、高松琴平電気鉄道(株)の安全輸送設備等の整備及び車両更新に要する経費を、国・県・沿線市町にて補助を行う予定としています。
人権問題に対する取組
人権問題に対する取組につきましては、町民一人ひとりが、自分の人権のみならず、他人の人権についても正しく理解し、町民の誰もが故郷として愛し誇れる、人権尊重都市琴平町の実現に向け、より豊かで、人権に満ち溢れた暮らしやすいまちづくりに向けて、部落差別をはじめとするあらゆる人権問題解決のため、引き続き人権教育・啓発活動に努めてまいります。
防災・防犯対策に対する取組
本年正月に発生いたしました能登半島の大地震に対し、犠牲となられた方へのご冥福、被災者へのお見舞いと、早い復旧復興をお祈り申し上げます。
今回の教訓から、災害はいつ発生するか想定は出来ないことが明確となり、災害に対する備えを改めて考えていかねばならないと思います。また、災害を止めることはできませんが、被害を少なくすることは行政の責務であります。南海トラフ大地震発生の可能性がある中、住民の皆様が安心安全に日常生活を送ることができるように防災のまちづくりを推進していくことが重要と考えています。
そのような中、昨年12月に、琴平町社会福祉協議会との間で「琴平町災害ボランティアセンターの設置・運営等に関する協定書」の締結を行い、大災害が発生時に、被災者・被災地支援を円滑かつ効果的に遂行し、地域の復興を推進するためのボランティアセンターの設置や運営に関する協力体制に関する協定です。
また、令和6年度においても町民の防災意識の向上、避難行動の確認のため町総合防災訓練を計画しております。
常日頃から住民の人命、財産を守る重責を担っている町消防団においては、令和6年度には、全国消防操法大会に出場が決定しております。今後とも地域防災力の要である消防団の訓練等を行い、いざという時にも誰もが安心して暮せるまちづくりを目指してまいります。
道路交通法の改正により令和5年4月1日から全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務になりました。自転車乗用中の交通事故で亡くなられた方は、その約6割が頭部に致命傷を負っています(H29~R3警察庁調べ)。自転車乗車用ヘルメットの着用率は、2023年7月の全国調査において、香川県は全国平均13.5%を下回る7.1%と全国ワースト12位。また、琴平町は県を下回る6.1%でした。こうした状況から、自転車利用者に「自転車乗車中の頭部保護の重要性」や「ヘルメット着用による被害軽減効果」について周知啓発するとともに、新年度から自転車ヘルメットの購入費用の一部を補助することにより、ヘルメットの着用促進を図り、交通事故防止及び事故被害の軽減を図ります。
空家対策に対しては、現在の「琴平町空家等対策計画」のデータを、令和5年度より見直しを行ったものに更新した後、地域に影響を及ぼす空家に対し、計画に基づき対処するとともに、効果的な対策を進めてまいります。
また、住宅等の倒壊予防及び自身の安全を図る目的の「民間住宅耐震対策支援事業」、「琴平町民間危険ブロック塀等撤去補助事業」、「老朽危険空き家除却支援事業補助金」など各種補助事業等を活用し、個々の相談に対応してまいたいと考えています。
昨今の少雨の影響などにより、早明浦ダムの貯水率も今まで以上に低い状況が続いています。水道水の安定供給に向け香川県広域水道企業団と協力するとともに、節水の呼びかけなど様々な協力を行ってまいります。
最後に、琴平町公共下水道事業会計について申し上げます。
これまで「官公庁会計」の「琴平町公共下水道特別会計」から、令和2年度より準備を進めておりました、地方公営企業法を適用した「公営企業会計」の「琴平町公共下水道事業会計」に令和6年度より移行いたします。
これにより経営状況の、より的確な把握及び経営健全化に取り組み、会計の透明化と普及率の向上に努めてまいります。
結びに
以上、令和6年度における町政運営につきまして、基本的な考え方と 施策の概要を申し上げました。
私が町民より琴平町政のご付託をいただいて、6年が経とうとしております。一歩ずつ、その先にある「未来の琴平」のために取り組んでいくことを 「信念」として、「勇気」をもって邁進してまいりました。これからも、 町民の皆さまをはじめ各方面からのご支援を賜りながら、町の賑わいと魅力をさらなる高みへと導き、将来にわたって「誰もが住みたい」、「誰もが行ってみたい」と思えるオンリーワンの町を目指し、各種施策に一層積極的に取り組んでまいります。そうした将来への夢と希望に対する期待に応えながら、高い理想や目標を掲げてその実現への道を開き、行動を起こさせるのがリーダーの使命と考えております。
「未来に何かを起こすには、勇気を必要とする。努力を必要とする。信念を必要とする。その場しのぎの仕事に身をまかせていたのでは、未来はつくれない。
未来にかかわるビジョンのうち必ず失敗するものは、確実なもの、リスクのないもの、失敗しようのないものである。」
これはマネジメントの父と言われるピーター・ドラッカーの言葉ですが、経営自体がリスクを伴う行為であり、経営からリスクを取り除くことはできません。このことは地域の経営、自治体運営でもいえることだと思います。できることは、イノベーションの機会を十分に考察し、正しいリスクをより多くとっていくことです。同様に、イノベーションも未来に対しての行動です。詳細な分析・検討をした後は、最後は経営者の勇気の問題になります。ドラッカーは言います。「イノベーションとは結局、勇気のことである」と。
琴平町を変えていくことは、故郷である琴平町に対する、誇りや愛着にもつながります。前例や固定観念に捉われることなく、即断即行により、希望ある未来を「勇気」をもって切り拓いていけば、「小さくても、みんなが笑顔で、幸せを感じるまち」が実現できるはずと信じております。
以上、令和6年度の私の町政運営に向けての施政方針と、施策の大要について申し上げ、議員各位並びに、町民の皆様のご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。