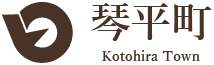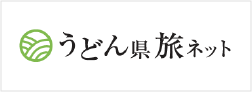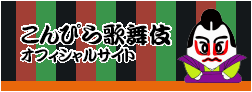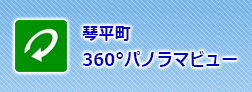こんぴら歌舞伎<外部リンク> こんぴーくん<外部リンク> ふるさと納税 こんぴらにんにく こんぴら石段マラソン 子育て世代包括支援センター 移住・定住補助金一覧リーフレット
本文
令和7年度施政方針
はじめに
令和7年度当初予算案をはじめ、諸議案のご審議をお願いするにあたり、私の町政運営に対する基本的な考え方と主要な施策の概要につきまして、説明申し上げます。議員各位及び町民の皆さまにはご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
令和6年は、年明けに発生した「能登半島地震」や夏の「奥能登豪雨災害」、さらに8月には当町にも初めて「南海トラフ地震臨時情報」が発表されるなど、災害への備えの重要性を強く認識させられた年となりました。町民の災害に対する危機意識も高まっており、減災防災対策の強化は待ったなしの課題となっています。
そういった中、本町の長年の懸案事項の一つであった「小学校や認定こども園の統合問題」については、統合小学校・統合こども園を併設し、この整備を進めることが決定し、次世代への教育保育環境の充実に向けて、着実に歩みを進めることができました。これまで、建設予定地の決定、買収用地の測量・鑑定、及び地質調査を行いました。また、「小学校・認定こども園統合新築検討委員会」を設置し、建物の配置などに関する意見を保護者や学校関係者等から伺いながら、基本設計業務を進めました。今後も保護者や町民の期待に応えるべく教育保育環境の充実に努め、子育てしやすい環境の整備を推進してまいる所存です。
また、学習環境の整備とともに災害時の避難所にもなっている琴平中学校の屋内運動場に、設置が望まれていた空調設備を完備するとともに、琴平、榎井、象郷の各小学校の屋内運動場にも、学校統合までの間の熱中症対応のための、移動式エアコンを2台ずつ配備しました。
福祉の面では、これまでの子ども、障がい者、高齢者などの分野別支援では対応が困難な複合化・複雑化した地域の福祉課題に対応するため、「重層的支援体制整備事業」を創設し、属性を問わない相談支援、参加支援及び地域づくりに向けた支援の3つを一体的に実施できる体制を整備しました。
観光や経済の面では、令和6年4月に5年ぶりに「四国こんぴら歌舞伎大芝居」が復活開催され、盛況のうちに17日間32公演を終えました。ようやく琴平にも春の風物詩としての賑わいが戻ったと感じました。通常時にも高松空港の上海、香港、台北への定期便、台中へのチャーター便、ソウルへの増便(週14便)、など国際便の就航拡大により、参道筋には多くのインバウンドによる外国人観光客が見られるようになり、コロナ禍からの力強い回復の兆しも見えてまいりました。また、物価高騰対策として、琴平町電子地域通貨KOTOCA事業において、チャージポイントの還元率を一定期間5%から20%に引き上げ、長引く景気低迷の影響を受けた地域経済の活性化を図りました。
人口減少や少子高齢化という課題に直面する一方で、本町を訪れる観光客数は着実に回復し、観光業を中心とした地域経済にも明るい兆しが見えてきています。特に令和7年4月からは、「第38回四国こんぴら歌舞伎大芝居」の開催に加え、大阪・関西万博、瀬戸内国際芸術祭と大規模なイベントが相次いで開催されます。この機会を活かし、観光地琴平の魅力を国内外に発信できる大きなチャンスの年となります。
一方で、物価の高騰、人手不足、また、世界的な政治状況の不安定さが、経済の先行きを不透明にしています。これまでの常識が通用しなくなりつつあります。
このような時期だからこそ、私たち行政職員には、より一層の創意工夫と実行力が求められています。AIをはじめとするデジタル技術を活用した業務の効率化、子育て支援の充実、高齢者福祉の拡充、そして観光振興と地域産業の活性化など、取り組むべき課題は山積しています。
これらのことを踏まえ、令和7年度当初予算につきましては、町民の誰もが未来へ向かって希望を描けるよう、本町の更なる進化に取り組むべき事業を予算化して編成しました。予算編成に当たっては、新時代を切り拓く琴平町らしさを深めていくこと、誰一人取り残さない持続可能な地域社会の実現を目指すこと、激甚化する自然災害への対策強化を進めること、そして、DX・GXの推進や地方への人の流れの強化等による地域経済の活性化及び新たな雇用の場の創出に取り組むこととしました。
その中でも特に、子ども・子育て関連施策や総合的な社会保障施策、ふるさと納税の取組、DXの推進を重視しております。
また、国の補正予算とも連動しながら、令和6年度12月補正予算から令和7年度当初予算まで、切れ目のない予算としました。
令和7年度の一般会計当初予算額は、対前年度比11.6%増の63億9,276万2千円、特別会計予算総額は25億7,237万9千円であり、全会計予算総額は89億6,514万1千円となりました。一般会計予算額としては、平成10年度以降、過去2番目に大きい予算規模となりました。
それでは、令和7年度の施策について第5次琴平町総合計画(基本目標)に沿って、ご説明を申し上げます。
1.笑顔で元気なまちづくり(保健・福祉・教育・文化・町政運営)
福祉に関する取組
令和7年は、団塊の世代が75歳以上の高齢者となることから、日本社会において国民の5人に1人が75歳以上となり高齢者の占める割合が大幅に増えることとなります。
本町では既に令和3年から高齢化率が40%を超えており、さらに令和6年3月には、後期高齢者が25%を超える状況となっています。
超高齢社会は、各分野における人材不足や医療費・介護費の増大、現役世代の社会保険料や介護保険料の負担増、医療・介護体制の維持など様々な影響を及ぼします。
本町としては、次世代を担う人材の確保や高齢者の健康寿命を延ばすことが重要であると考え、令和6年3月に策定した6か年計画の「第3次地域福祉計画・地域福祉活動計画」を基に、「重層的支援体制整備事業」の取組をさらに充実させ、「人づくり」、「地域づくり」、「まちづくり」、「仕組づくり」を中長期的な視野で築き、「地域共生社会の実現」を目指してまいります。
そのために、まずは、フォーマルな社会資源(制度化された資源)としての各種福祉制度に基づく行政・公的サービスを必要な方に届けるよう努めます。町民のニーズを的確に把握し、社会福祉協議会や地域包括支援センター、福祉事業所等関係機関との連携を強化し、情報共有を進めてまいります。
また、前述の関係機関に加え、インフォーマルな社会資源(制度化されていない資源)として、町民や、自治会を始めとするボランティア団体の皆様の協力のもと、行政だけでは解決できない複雑な課題を解決できる体制づくりを進めてまいります。
さらに、令和6年度初めて町内各地区で開催しました「地域づくり座談会」については、今後も継続して取り組んでまいります。この座談会を通じて、町民の意見やアイデアを積極的に取り入れ、地域の課題を町民と行政で共に考え、解決策を見出していく取り組みを続けていきます。
子育て支援に対する取組
令和6年度は、国の子育て世代に対する施策が大きく変更されました。特に、児童手当においては所得制限の撤廃や給付金額の見直しに加え、第3子の取り扱い方を拡大したことで、特に3子以上がいる家庭にとっては給付金額が大幅に増加しました。また、こども園の保育教諭の配置基準の見直しにより、より細やかな保育に努めることが可能となりました。
琴平町においては、令和7年度より第3期「琴平町子ども・子育て支援事業計画」の計画年度へ移行いたします。
子ども・子育て支援事業計画は、教育・保育及び地域の子ども・子育て支援を総合的に進めるための基本的な指針となるものです。子育てしやすい環境の充実や親子の健康の確保に加え、様々な状況の子どもへの対応等のキメ細かな取組の推進を図るものです。これらを実現するために、本町では令和7年度より「こども家庭センター」を令和8年度、子ども・保健課内へ設置するため準備を進めます。
「こども家庭センター」では、母子保健サービスを子育て支援を必要とする妊産婦や子ども、子育て世帯に確実に届けるため、支援メニューの体系的なマネジメントを行う「サポートプラン」を作成することや児童虐待防止や社会的擁護・ヤングケアラー支援等についても対応してまいります。
また、令和6年度より取り組んでおります、携帯電話などから産婦人科医・助産師・小児科医に気軽に相談できる「産婦人科・小児科オンライン」につきましても安心して妊娠、出産、子育てができるよう引き続き支援を行ってまいります。
保健事業に対する取組
町民の誰もが、より長く元気に暮らしていくための基盤として、健康が大切であることは誰もが認識していると思います。しかし、その反面、健康を自分ごととしてしっかり認識し、健康に対する取組を行っている人は少ないのが現状です。
健康づくりは、個人個人の「自助努力」が大前提にあることから、まずは、健康でいるためのヒントを町民へ届けることから始め、特定健診の受診勧奨を通じて健康意識の向上に努めてまいりたいと考えています。
また、令和7年から帯状疱疹ワクチンの接種が国のメニューに加わったことから、個人負担は必要ですが町の補助対象として実施してまいります。
教育に対する取組
教育は、人格の完成を目指し、心身ともに健康な国民の育成を期して行うことを目的に、学校教育や社会教育などにおいて行うことになっています。
学校教育においては、令和7年度も教育委員会が進めている「自立に向かう教育と学校で学びたいと思える環境づくり」を一層推進し、次代を担う子どもたちの自主性と創造性を培うとともに、確かな学力を身につけ、豊かでたくましい心と体を育てる教育の充実に努めてまいります。そのため、これまで整備してまいりましたGIGAスクール構想に基づき、児童生徒一人一台の夕ブレット端末や大型電子黒板等を有効活用し、すべての児童生徒がより質の高い教育を受け、必要なスキルを習得するよう努めてまいります。新年度においても次世代を担う子どもたちがICTを活用して新しい時代に必要な資質・能力が身につくように育んでまいります。
また、小中連携による英語学習の推進も引き続き図ります。英語に関する町単独の「英語指導助手」を令和6年度より1名増員し、英語教育の充実や国際理解教育の推進を進めるとともに、児童・生徒の国際感覚やコミュニケーション能力を高めるよう取り組んでおります。現在、小学校1名、中学校1名、合計2名の配置となっております。なお英語力向上のために「英語検定の受験料の全額補助」も引き続き行います。
そのほか、自己肯定感や自己有用感の醸成をあらゆる場面を通じて行うとともに、令和6年度6月より2名教育委員会に常駐しているスクールソーシャルワーカーを活用し、不登校などの悩みを持つ子どもたちへの支援を町全体で進めてまいります。
令和5年度に再開いたしました台湾新北市瑞芳区並びに瑞芳中学校との国際交流では、令和6年度は琴平中学校の生徒を台湾に派遣しました。令和7年度は、琴平中学校に瑞芳中学校生徒を招いて姉妹校交流を行います。
学校給食費については、物価高騰の影響から、値上げを検討せざるを得ない状況にあります。しかしながら、保護者の負担が増えないようにするため、給食費の値上がり部分については町が負担し、保護者の負担いただく給食費は据え置くことで応援してまいります。子どもたちが安心して給食を食べることができる環境を維持するため、引き続き努力してまいります。
さらに、ふるさとことひらを愛する教育や様々な人権問題について主体的に解決する児童生徒の育成については、これまでの成果をさらに積み上げ、より充実したものにするよう取り組んでまいります。
また、町としての一貫した教育理念のもと、共通認識をもって教職員が指導に当たり、子どもたちが新しい時代にあった、お互いの学び合いや、切磋琢磨できる充実した教育環境を提供できるよう、「休日等における学習支援」にも令和7年度から取り組んでいきたいと考えております。あわせて、中学校図書館の一般開放については令和7年度から取り組んでまいります。
統合小学校及び統合認定こども園は令和11年4月に開校・開園を目指し、令和6年度、建設予定地も決まり着実に進んでいます。令和7年度は、「建設工事実施設計」の作成により統合小学校・統合認定こども園の校舎・園舎も具体化してまいります。
さらに、令和8年度以降、統合小学校の校名、校歌、通学路、制服などのソフト面を「統合準備委員会(仮称)」で決めていく予定です。
皆様のご理解もいただきながら、子どもたちの教育環境を最優先に考え、統合小学校整備事業並びに統合認定こども園整備事業に取り組んでまいります。
一方、社会教育においては、生涯教育や家庭教育の大切さを共有するための取組や支援について、検討し、これからも引き続き小さな子どもから高齢者まですべての方が生涯にわたって学び続けることができる環境整備に努めてまいります。
令和の耐震対策工事後、旧金毘羅大芝居は魅力ある国指定重要文化財として、多くの方々にご覧いただいております。旧金毘羅大芝居を含め、町内にある文化財の保護、保存・活用に関する取組についても、町文化財保護協会とともに、徐々にではありますが進めており、天然記念物である大センダンについても、令和5年度に策定した「琴平町の大センダン保存活用計画」に沿って、令和6年度に緑地化等の基本設計を基に、令和7年度に電柱、ブロック塀などの工作物を撤去するとともに、実施設計の策定に取り組みます。新たに任用予定の文化財に関する専門員とこれまで任用している専門員をフルに活用し、今後とも、歴史と伝統、文化のあふれる町づくりや、前回の改編から30年近くたっている町史のそれ以降の編さんに向けての準備など、文化行政を推進してまいります。
いこいの郷公園及びヴィスポことひらにつきましては、平成16年にオープンし、20年が経過いたしました。令和6年度から令和10年度までの5年間は「いこいの郷パートナーズ」を指定管理者として運営しておりますが、スポーツ施設から、遊具等も整備し小さい子も遊べる総合的な健康増進施設の役割を重視し進めてまいりたいと考えています。また、施設の経年劣化等による不具合等を防ぐため、令和5年度に策定した琴平町公園長寿命化計画に基づき設備の更新などを順次進めてまいります。令和7年度においては、メインアリーナの屋上防水の改修工事を進めてまいります。
町政運営に対する取組
琴平町のまちづくりの基本的な指針である「第5次琴平町総合計画 基本構想」の最終年度を迎えることから、令和7年度には、琴平町総合計画審議会に諮問のうえ「第6次琴平町総合計画 基本構想」を策定いたします。
また、10月には全国一斉に「国勢調査」が行われます。住んでいるすべての人と世帯を対象とする、国でも最も重要な統計調査です。全国的に人口が減少しているなか、琴平町も同様に人口の減少が続いております。「琴平町人口ビジョン(令和7年3月作成)」では、課題として、
・人口減少に歯止めがかかってない現状。
・未婚率が高い。
・主要産業の高齢化に伴う人材不足が懸念される。
・成人となったタイミングでの転出が超過している。
ことがあげられております。人口構造のさらなる高齢化を抑制するためにも、若年層の人口流出の抑制、結婚・出産におけるサポート、主要な産業の労働力の確保に取り組むことが今後の課題としております。令和42年(2060年)に約6,000人の人口確保を目標にとしたうえで、まずは、さらなる移住施策を進めて転入者増を、現住されている方を引き続き定住いただき、転出者減を図らねばなりません。
そこで、次代の琴平町を担う若い世代の方々の発想を大切にしながら、若者のニーズをはじめ、町民等の意見や提言をしっかり取り入れ、「住みたいまち」琴平町、持続可能なまちづくりの推進をしてまいります。
持続可能な行財政運営と質の高い行政サービスを次世代に引き継ぐためには、本町の公共施設等の見直しが必要です。
統合小学校及び統合認定こども園については、令和11年度の開校開園に向けて引き続き取組を進めてまいります。
また、本役場庁舎の長寿命化に向けた改修工事等についても取り組まなければなりません。
庁舎が安全かつ快適に利用できることは、職員の安全や働きやすさ、さらには町民サービスの向上にも直結するため、令和7年度においては、令和6年度に実施したプロポーザルによる公募を通じて選定した事業者から提出された資料や技術提案書を基に、今後の調査・計画の立案や検討、構造計算など具体的な検証を行いながら、基本構想等を策定していく予定です。
この基本構想等の策定は、庁舎の機能性や安全性を高めるために非常に重要なステップであり、私たちの行政サービスを支える基盤となります。特に、庁舎は、災害時の地域の拠点として機能することが求められており、そのため、災害時における安全性や迅速な対応が可能となるよう、設計段階からしっかりと考慮していく必要があります。職員が安心して働ける環境を整えることは、結果として町民の皆様へのサービス向上にもつながってまいります。
行政のデジタル化についても、早急な取組が求められています。国は、2023年度を初年度とする5か年の新たな「デジタル田園都市国家構想総合戦略」を閣議決定し、「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」の実現に向け、デジタルの力を活用しつつ、地域の特性を活かしながら地方の社会課題の解決や魅力向上の取組を加速化・深化することとしています。
本町においても、中讃広域行政事務組合の自治体DX推進事業などを活用しながら、職員の意識向上や実施する業務の洗い出しなどに取り組みます。
また、令和6年11月には新たに地域おこし協力隊員を委嘱し、四国初の「地域おこし協力隊DAO」の取組を開始しました。AIを活用した業務の効率化、研修等による職員の資質向上、さらなる情報発信等を推進してまいります。このプロジェクトを通じて、Web3技術を活用した新たなデジタルコミュニティの形成を目指します。
自治体が使用する情報システムに対する国が示す標準化基準への適合が計画されており、現行システムから「標準化・共通化したシステム」へ移行する期限が令和7年度中と決められています。本町においても、関係各課、ベンダー(システム委託業者)、中讃広域2市3町と連絡調整を図りながらスムーズな移行ができるよう、作業を進め、令和8年1月から新しいシステムで運用します。これにより自治体運営の効率化、町民サービスの向上を図ってまいります。
令和3年に電子地域通貨「KOTOCA」事業がスタートしました。引き続きこの事業を推進するとともに、高齢者に対するスマートフォンを新規に購入した際の助成事業をはじめ、スマホ教室の開催など、高齢者のデジタルデバイド、つまり、インターネットやPCなどを活用できる人とできない人の間に生まれる格差の解消に取り組んでまいります。
近年、地域コミュニティの中心である自治会への加入率が、本町では5割を切る状況にあります。防災や防犯、高齢者・子どもの見守り、居場所づくりなど、地域として対応すべきニーズが変化、複雑化する中において、加入率減少は、地域力の低下につながる不安要素となっております。そこで、地域共生社会を確立する観点からも、行政だけでなく関係団体とともに令和6年度より取り組んでいる「地域づくり座談会」を引き続き開催し、地域活動を推進する上での地域の現状課題を共有し、その解決方法や今後必要となる取組について検討することにより、町民が安心して暮らせるまちづくりを推進していく考えであります。
ふるさと納税に対する取組
ふるさと納税は、本町にとって貴重な財源となっています。各種ポータルサイトの追加登録や新しい返礼品の開拓等により、令和5年度、6年度にかけて寄附額も増加しています。令和7年度においても、引き続き、ポータルサイトのブラッシュアップや新規返礼品の開拓を進めてまいります。このほかにも、返礼品を複数回に分けて発送する「定期便」や異なる返礼品同士を組み合わせた「セット品」の作成など、新たな戦略を実施し、財源の確保に取り組む所存です。「企業版ふるさと納税」制度においては、令和7年度以降も3年間延長することが「令和7年度税制改正の大綱」に盛り込まれており、引き続き本町の地方創生の取組に対して企業からの寄附を募ります。募集をする地方創生の事業内容、企業版ふるさと納税を利用した税制メリット等を広くPRするとともに、企業を訪問して寄附のお願いをするなど積極的な働きかけを行うことにより財源の確保に努め、地方創生のさらなる充実・強化を図ってまいります。
2.にぎわいのあるまちづくり(観光・経済)
観光・経済に対する取組
新型コロナウイルス感染症の5類移行により、旅行需要の高まりや国際路線の通年運航、増便などによるインバウンド(訪日客)の増加により、国内外からの観光客が増え、コロナ拡大前の9割程度回復してきました。しかしながら、円安を背景とした燃料費や物価の高騰などにより、町内事業者を取り巻く現状は依然として厳しい状況です。引き続き、プレミアム商品券発行事業やKOTOCAチャージポイント付与事業などを通じて、個人消費の回復や地域経済の活性化を図ってまいります。
4月には、令和6年に引き続き、「第38回四国こんぴら歌舞伎大芝居」を開催いたします。令和7年は小屋の創建190年、大芝居が始まって40年の節目の年でもあることから、その成功に向け、地域や関係者の方々とともに、町全体で取り組んでまいります。
また、同時期に「大阪・関西万博」や「瀬戸内国際芸術祭」も開催されることから、インバウンドを見据えた受け入れ態勢のさらなる充実や他の自治体との横の連携、広域観光の推進など、金刀比羅宮や観光関連団体等との、情報共有や連携強化により、持続可能な観光地域の魅力発信や誘客事業に取り組んでまいります。
令和7年度は、琴平町温泉事業基金を新設することにより、こんぴら温泉郷の温泉事業の健全運営に努めてまいります。
観光客の受入体制の整備については、AIカメラを用いた表参道の人流データの集積や町営駐車場の自動化を視野にいれるなど、渋滞緩和について、データ収集・分析を行いながら、動線の見直しや、内外に向けたアピールなどの対策等を講じてまいります。
商工部門におきましては、「(仮称)琴平町中小企業振興基本条例」の制定を目指し、琴平町商工会と協議しながら、町内中小企業の活性化に取り組んでまいります。
また、魅力ある地域づくりのため、地域おこし協力隊員と協働し、SNS等を活用して、本町の情報発信や地域ブランド、地場産品の開発・PR等を行っていきます。令和6年度は、台湾フェスや台湾朝食交流会といったイベントを契機に、海外文化の理解と国際交流の機運醸成に取り組んでまいりました。令和7年度も引き続き実施してまいります。
農業に対する取組
我が国の農業は、農業従事者の著しい高齢化、後継者や担い手の不足により農業従事者が激減していることが喫緊の課題となっています。経営状況については、作付面積の減少、昨今の異常気象や農作物の生育不足により、販売価格は高騰していますが、燃料・種子類等も含めた資材費等の値上がりにより不安定な状況が続いています。
令和7年度においても、農地維持管理費補助金を継続して交付し、地産地消の推進をはじめ、他県での促進販売の実施及び卸売市場関係者との協議を行い、販路の拡大や農産物の品質向上、地域農業の振興、発展を進めていくとともに、収入保険に新規で加入される農家に対しての補助や、担い手・多様な人材の支援として農機具等の購入補助を行うなど、持続可能な農業経営の安定を応援してまいります。
また、土地改良事業、多面的機能発揮促進事業の予算を拡充することにより、農業施設及び地域環境の保全を行ってまいります。
なお、農地の利用権設定については、農業経営基盤強化促進法により、令和7年4月1日から農地機構を通した手続きとなります。
3.安全・安心なまちづくり(防災・環境・住民生活・インフラ整備)
環境・住民生活に対する取組
令和9年度より、ごみ焼却処理施設をクリントピア丸亀に移行するにあたり、コストの増加を抑えつつ、町民サービスの低下を招かないよう準備を進めてまいります。その一環として新たな塵芥収集車を購入し、収集作業がより円滑に進むよう努めてまいります。
さらに、町民の利便性向上に資するために、令和6年度スタートさせた「ハッピーマンデー可燃ごみ収集」は、多くの町民から好評をいただいております。
令和7年度に向けては、この流れをさらに加速させるために、資源ごみ収集について新たな取組を行います。具体的には、資源・プラごみを出される際には「プラマーク」を確認しなくても、100%プラスチックであれば資源として出すことができるよう、県下では初の取組を4月からスタートさせます。これは、国のプラスチック資源循環法(プラ新法)に準拠したものであり、可燃ごみや不燃ごみの量を減らすことを目指しています。これにより、SDGSへの貢献と交付税措置によるコストカットが図られることから、町民の皆様への浸透に努めてまいります。
また、令和6年4月から行っております、町の塵芥収集員が空き時間を利用して金丸座周辺や参道筋などの観光人口密集地でのゴミ拾い活動を実施する「KOTOHIRA CLEAN KEEPER」についても、引き続き実施する予定です。
以前は観光シーズンになると道端に多くのごみが散見されましたが、ポイ捨てしにくい環境が少しずつ整いつつあると手ごたえを感じています。
「きれいなまち」の印象をPRすることで、リピーターやいわゆる「愛着人口の増加」に繋げていくことが目標です。これらの取組を通じて、町民の皆様が誇りに思えるような美しい環境づくりに努めてまいります。
公共交通機関への支援も継続して行います。安全・安定した運行の維持と利便性・快適性の向上による利用者の増加を図るため、高松琴平電気鉄道(株)の安全輸送設備等の整備や車両更新に要する経費を、国・県・沿線市町にて補助を行う予定としています。
人権問題に対する取組
人権が尊重され、差別や偏見のない明るい社会を実現するためには、学校、家庭、職場、地域など様々な場において、人権教育・啓発を行うことが重要です。町民の誰もが故郷として愛し誇れる、人権尊重都市琴平町の実現に向け、町民一人ひとりが、人権問題を自分のこととして捉え、豊かな人権感覚を育んでいくための人権教育・啓発活動を推進してまいります。
また、情報化の進展に伴って、インターネットの匿名性を悪用し、全国の被差別部落の一覧が掲載された事案をはじめ、インターネット上には、部落差別を助長する書き込み及び被差別部落の画像投稿事案が後を絶たない状況であります。引き続き、人権・同和問題解消に関する研修等効果的な部落差別解消に向けた教育・啓発を関係団体からの助言を得ながら確実に実施するとともに、令和6年5月に制定された情報流通プラットフォーム対処法に同和問題を盛り込むよう要望してまいります。
防災・防犯対策に対する取組
令和7年1月に日本政府地震調査委員会が、今後30年以内の南海トラフ地震発生確率を従前の「70~80%」から「80%程度」に上方修正する報告書を発表しました。自然災害の発生を止めることはできませんが、被害を軽減することは行政の責務です。町民の皆様が安全・安心に日常生活を送ることができるよう、防災のまちづくりを推進することが重要です。能登半島地震を受け、国が令和6年9月に防災基本計画を修正したことに伴い、本町の防災・減災対策の基本指針となる「地域防災計画」をその修正内容に添うよう令和7年度中に見直します。また災害時、他の自治体等からの応援を効率的に受け入れることができるよう、「琴平町人的応援の受入れに関する受援計画」を策定したいと考えております。また、能登半島地震の教訓を避難所の生活環境の向上に活かしていくため、災害時の通信インフラの強化、断水時の給水環境整備、簡易トイレ等の備蓄強化に努めてまいります。
令和7年11月には、香川県との合同で総合防災訓練を計画しております。消防団や防災関係各機関との連携強化を図るとともに、町民の防災意識の高揚を図ってまいります。
また、警察と連携し、情報共有による犯罪の未然防止と事件の早期解決に努め、防犯カメラ設置に対する補助を行うなどの取組を引き続き推進します。
道路交通法の改正により令和5年4月1日から全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務になりました。自転車乗用中の交通事故で亡くなられた方は、その約6割が頭部に致命傷を負っています。引き続きヘルメットの購入費用の一部を補助するとともに、ヘルメットの着用を周知、啓発してまいります。
交通安全対策としては、琴平町とまんのう町が隣接する琴平町榎井地区・まんのう町大橋地区において、区域を定めて速度規制をし、それを補完する為の凸(とつ)型路面等の物理的デバイスを組合せて設置する事業を計画しています。
空き家対策としては、引き続き香川県の空き家バンク制度を活用した「琴平町空き家バンク制度」を推進するとともに、窓口での相談受付など、地域に影響を及ぼす空き家に対し、効果的な対策を進めてまいります。
また、住宅等の倒壊予防及び自身の安全を図る目的の「民間住宅耐震対策支援事業」、「琴平町民間危険ブロック塀等撤去補助事業」、「老朽危険空き家除却支援事業補助金」など各種補助事業等を活用し、前年度に引き続き個々の相談に対応していきます。
さらに、令和7年度から香川県が過疎地域等における人口減少に歯止めをかけるとともに、空き家の利活用を促進するため、国の「空き家再生等推進事業」に基づき、空き家対策の新規事業を創設したことを受けて、本町も新規事業として「琴平町中間管理住宅事業(仮称)」を計画しています。この事業は、町が民間の空き家を借り上げ、国・県の補助金を充当して、改修工事を行い、入居者の募集を行って貸し出すものとなります。貸出期間は、概ね10年間を予定しており、改修費用等を10年で回収できるような家賃設定を計画しています。比較的程度の良い空き家の有効活用を図りたいと考えています。
琴平町の公共下水道事業は、令和6年度から公営企業会計へ移行したことにより、経営状況や資産の明確な把握が可能となりましたので、将来の中長期的な経営計画や構築物の更新計画の策定に役立て、経営の健全化と普及率の向上に努めてまいります。
結びに
以上、令和7年度における町政運営の基本的な考え方と施策の概要について申し上げました。
私が令和4年6月に2期目の町長に就任してから、2年10か月が経過しました。この間、議員各位ならびに町民の皆様には、町政に対する深いご理解と多大なるご協力を賜り、心より厚く御礼申し上げます。
長引いたコロナ禍による社会の変化をはじめ、人口減少・少子高齢化の進行、地域経済の停滞、日常生活における支援ニーズの多様化、さらには地域コミュニティの担い手不足といった課題が深刻化しています。行政運営においては、社会保障関連の支出が増加し続けているうえ、公共施設や社会インフラの老朽化が一斉に進み、施設整備においては集約化や大規模な補修・建替えが求められています。
これらの課題を乗り越え、未来への道筋を見出すためには、目の前の困難から目を背けることなく、持続可能な地域社会の実現に向けた取り組みを加速させる必要があります。
また、国の動向を見ますと、石破総理は「地方創生2.0」として「令和の日本列島改造」を強力に推進する方針を示しました。特に「若者や女性にも選ばれる地方」の実現では、都市と地方の2地域を拠点とした活動の支援や「ふるさと住民登録制度」の検討、地方での賃金上昇を促進する環境整備が掲げられています。さらに、「地方イノベーション創生構想」の実現では、官民連携による文化・芸術・スポーツの振興を通じ、観光産業の活性化を進めることが重視されています。
私たちは、この国の施策を最大限に活用しながら、民間組織・団体との連携を深め、広域連携や集約化、シェアリングの視点も取り入れ、地域の力を結集してまいります。
そして、「若者や女性にも選ばれる地方」という国のメッセージは、努力する地方自治体を後押しするという力強い意思の表れです。私たちは琴平町の「強み」を活かし、「弱み」を克服しながら、「生活・文化・観光の調和」がとれた真の「琴平町らしさ」を追求してまいります。
本町は小規模自治体ではありますが、だからこそ可能な「身近な行政」を実現し、きめ細やかな福祉サービスと迅速な課題対応を心掛けてまいります。「小さくても、みんなが笑顔で幸せを感じる町」を目指して、町民の皆様との対話を重ねながら、誇りを持って暮らせる琴平町をともに創り上げていきたいと考えています。
大人も子どもも、町民みんなが「誇り」を持てる琴平町へ。 小さな町だからこそ実現できる、一人ひとりの顔が見える行政、心の通う対話を大切にしながら、町政運営に全力を尽くしてまいります。
以上、議員各位ならびに町民の皆様の一層のご理解とご協力を賜りますよう、心からお願い申し上げます。