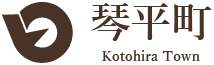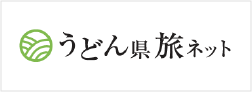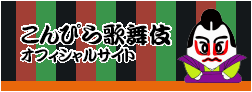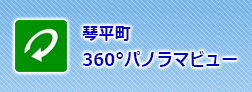本文
福祉医療制度について
琴平町では、「重度心身障害者等医療費助成制度」「ひとり親家庭等医療費助成制度」「子ども医療費助成制度」につきまして、香川県内での医療機関(一部接骨・鍼灸マッサージ院等は除く。)において、受診される場合は、自己負担分が原則として不要となります。
なお、「後期高齢者医療制度」につきましては、令和2年8月1日診療分から自動償還払いとなります。
※自動償還払いとは、医療機関等の窓口にて一旦お支払いいただき、原則診療月より3ヵ月以降に指定口座へ支給になります。(これまで提出いただいていた医療費支給申請書の提出は原則不要です。)
福祉医療とは、「重度心身障害者等医療費助成制度」「ひとり親家庭等医療費助成制度」「子ども医療費助成制度」の制度の名称です。
琴平町の福祉医療の優先順位
出生・転入の日の日から9歳に達した日以後の最初の3月31日までは「子ども医療」が優先です。(1)
(1)の期間が終了した翌日(9歳に達した日以後の最初の4月1日)からの医療の優先順位は次のとおりです。
(2)重度心身障害者等医療 → (3)ひとり親家庭等医療 → (4)子ども医療
※「(4)子ども医療」を受給中に「重度心身障害者等医療」、「ひとり親家庭等医療」の資格を持った子どもは、そちらの資格が優先されます。
※福祉医療の優先順位により、途中で資格が変更される場合があります。
受給資格者証について
受給資格者には、医療費受給資格者証が大変重要です。
窓口受付の際には、マイナ保険証等とともに、毎回必ず受給資格者証を提示してください。
受給資格者証の提示がない場合は、窓口負担を支払う必要がありますので、ご注意ください。
ただし、保険給付対象外の部分(検診・予防接種・薬の容器代・差額ベッド代・入院時食事療養費等)につきましては無料化の対象外ですので、これまでと同様に窓口で支払いしてください。
受給資格者証の更新について
重度心身障害者医療・ひとり親家庭等医療対象者の方については、毎年8月1日が更新日となります。所得要件を満たし、更新できる方には7月末までに新しい受給資格者証を送付いたしますので、有効期限の切れた受給資格者証は子ども・保健課まで返納してください。
所得の申告がなかったり、転入等により本人及び扶養義務者の所得の確認ができない場合には、受給資格者証をお渡しできない可能性があります。
※転入の場合は、所得証明書または同意書の提出をお願いします。
健康保険の変更、住所が変わった場合
加入保険が変更になると、請求先も異なりますので、所定の申請書により手続きをお願いします。
(お持ちいただくもの)
- 変更後の健康保険の資格情報が確認できるもの(受給資格者の名前が載ったもの)
- 本人確認書類
- 受給資格者証
また、受給資格者が、琴平町外へ転出した場合や受給資格がなくなった場合には、有効期限の有無に関わらず資格がなくなります。必ず受給資格者証を子ども・保健課まで返還してください。
その他届けが必要な場合
- 生活保護をうけるようになった場合
- 「重度心身障害者等医療」、「ひとり親家庭等医療」に該当することとなった場合
- 氏名等が変更した場合
- 受給資格者証を紛失、破損した場合
※手続きをお忘れになると、自己負担分をお支払いしていただく場合があります。
償還(払戻)申請について
以下の場合はこれまでどおり償還払いとなりますので医療費支給申請書を提出してください。
- 受給資格者証を提示されなかった場合
- 県外の医療機関または一部接骨・鍼灸マッサージ院等を受診された場合
(申請に必要なもの)
- 領収書または医療機関等の証明を受けた福祉医療費助成申請書
- 受給資格証
- 窓口に来られる方の本人確認書類
申請期間(受診の翌月から5年)が過ぎた場合は、お支払いできませんのでご注意願います。
注意事項
次のような場合は福祉医療の対象とはなりません。
- 自立支援(育成)医療、養育、小児慢性特定疾患治療研究事業などの国の公費医療制度が適用される場合は、それらの公費医療が優先適用されます。
- 災害共済給付(独立行政日本スポーツ振興センター)制度に加入している子どもが幼稚園・保育所・小中学校の管理下における負傷・疾病・障害等を負った場合は、同センターから災害共済給付が優先されます。
- 医療費保険対象外の経費(検診・予防接種・薬の容器代・差額ベッド代・入院時食事療養費等)
- 生活保護を受給している場合
- 交通事故などの第三者の行為による治療
医療費の適正受診にご協力ください。
福祉医療費助成制度は、町の負担分と県の補助金で運用されています。
また、医療費が増加すれば、保険料や税金の負担が大きくなります。
- かかりつけ医を持ちましょう。
- 重複受診をやめましょう。
- 診療時間内の受診を心がけましょう。