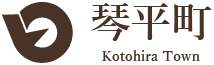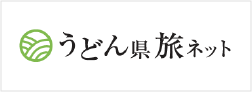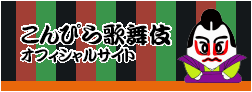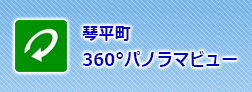こんぴら歌舞伎<外部リンク> こんぴーくん<外部リンク> ふるさと納税 こんぴらにんにく こんぴら石段マラソン 子育て世代包括支援センター 移住・定住補助金一覧リーフレット
本文
日常の活動
1.防災知識の普及
1)訓練や防災施設見学参加の呼びかけ
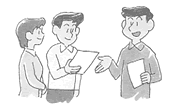
2)講演会、座談会の開催や防災映画、ビデオの上映

3)パンフレット、ミニコミ紙の発行
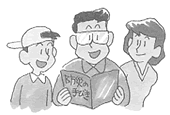
4)地域の防災史のとりまとめ

5)地域内危険箇所、危険原因の調査と周知
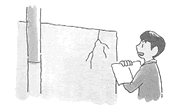
6)防災マップづくり
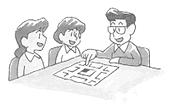
2.家庭における防災対策の普及
地域の災害対策は、各家庭での事前対策から始まります。次のような家庭の事前対策について周知徹底する必要があります。
1)住まいの安全度(地盤やブロック塀なども含め)のチェックと補強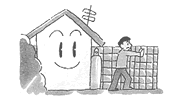
2)家具などの転倒防止とガラス飛散防止対策
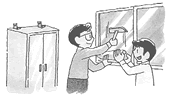
3)調理器具、暖房器具などの火気使用設備機器の安全点検と出火防止
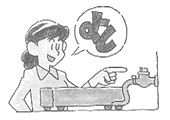
4)石油類、スプレー、プロパンガス等可燃性物品の安全点検

5)初期消火や応急手当の方法

6)非常持ち出し品の準備
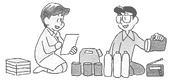
7)避難経路、避難所の確認

8)地震がおきたときの役割分担
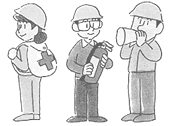
3.避難方法の確認と周知
避難経路・避難所、災害状況(昼か夜か、水害か地震か、風向きなど)によって違ってきます。日頃から、いろいろな状況を想定して災害時に一番安全な避難経路と避難所を複数確保する必要があります。避難が必要となったとき、自主防災組織では避難誘導班が手分けをして各戸を回るなどの方法により、次の情報を伝達して避難を促します。従って、自主防災組織は、事前にこれらのことを調査し、把握しておくとともに、基本的な事項については、住民に周知しておかなりればなりません。
1)避難の時期
うわさやデマにまどわされず正しい情報を。
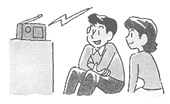
2)一時集合場所、避難経路避難所
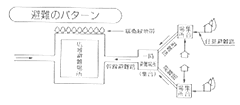
3)非常持ち出し品の注意
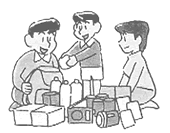
4)その家の避難人数や要介護者の状況
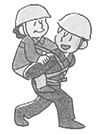
お年寄り・病人など
- 援助が必要なときは複数の人間で対応する。
- 急を要するときは、ひもなどで背負って安全な場所へ避難する。
4.地域内団体との協力活動など

地域内の企業、病院との協力体制や、老人ホーム、社会福祉施設などに対する援助についても、平常時から注意しておいてください。
場合によっては、応援や援助についての協定を締結するとともに、合同訓練の実施も大事なことです。
5.防災資機材の整備・点検
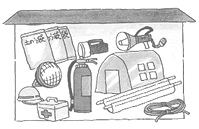
自主防災組織で整備する防災資機材は、消火器、バール、ハンマー、ロープ、救急セット、担架、携帯拡声器などです。
いざというとき、すぐにでも使えるように定期的な点検や取扱訓練をしておくことが大変重要です。
6.防災訓練の実施
1)情報収集伝達訓練
自主防災組織を中心に、地域内の被害情報を集めたり、市や防災機関からの情報を地域に伝える訓練。
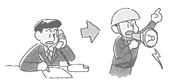
2)消火訓練
みんなでバケツリレーや消火器による消火訓練を行い、協力して消火活動を行う訓練。
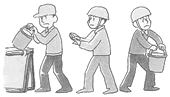
3)救出救護訓練
家屋が倒れたり、家屋の下敷になった人の救出活動や、落下物に当たって、<ケガ>をした人などの応急手当、担架搬送の方法などを身につける訓練。
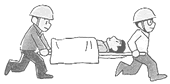
4)避難誘導訓練
避難の要領を学び、指定された避難場まで、早く安全に避難できるように実際に歩く訓練。
身体的弱者の避難訓練も重要です。
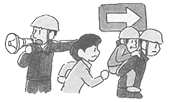
5)給食給水訓練
水や熱源が制限されている状況での炊き出しや乾パン、飲料水などの配分訓練。

6)その他地域の特性に応じた訓練(水害に対する訓練など)
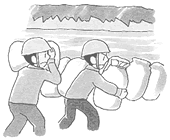
7)個別訓練で体得した知識技術を併せた総合的な訓練
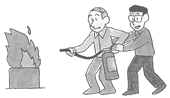
8)訓練計画のたて方
- 目的に応じた計画を立てる。
- 正しい知識・技術を覚えるために、消防署などの指導をうける。
- 原則として、個別訓練を実施したのち、総合訓練を実施する。
- 訓練終了後、検討会を開催する
- 多くの人に参加してもらえるように、その都度、曜日や時間帯を変える。
- ときにはゲーム形式やあそび感覚を取り入れる。
- E-mail: